東京下町のお祭りは、台東区にある下谷神社を皮切りにスタートする。
祭りの季節到来に、町中が活気付き、
その熱気は、熱病のように東京中に広がっていく。
町内の詰所から流れるお囃子の音
法被やふんどし姿の担ぎ手の姿が
祭り到来の合図を告げる。
6車線もの浅草通りは、神輿のために片側通行となり
警察官が神輿のために道を作る。
道路には、天狗や馬、お囃子が練り歩き
地響きのような掛け声の中から、
悠然と神輿が現れる。
揺らしすぎず
安定した神輿の姿は、下町の担ぎ手たちの誇りだ。
神輿の周りでは花棒を争う喧嘩が絶えず
担ぎ手を守る近所のおじさん達も、
この日ばかりは、法被姿が男らしく、
粋で頼もしく目に映るものだ。
威勢のいい掛け声と
歓声
怒鳴り声と
警察官の笛の音
それらが一つになって、祭りならではのリズムを刻む。
担ぐ者も見る者も顔を上気させ
あたりは汗とお酒と法被の匂いが充満していた。
大音量で町を走る街宣車までもが、
神輿のそばでは車を停めてスピーカーを切り
神輿に道を譲り、敬意を払う
町全体が一体となる。
氏子たちは誇らし気に町を練り歩く。
下町のお祭りは特別だった。
幼かった私もこの日ばかりは一丁前に、
目元に赤いラインを引いて唇に紅をさし、
鯉口シャツに
股引(ももひき)
どんぶり(腹掛け)姿で
地下足袋を履いた。
そして、ねじり鉢巻きをして
最後に、わらじを履いた。
わらじは父が足のサイズに合わせて編んでくれた。
足元がスニーカーだったら台無しだろ
祭りの時のこだわりは、徹底されていた。
その自負と喜びは幼くとも伝わってくるものがあり、
私は足を差し出して
慣れぬ藁の香りにくしゃみをしながら
父が編む手元をじっと眺めていた。
足にぴったりと編まれたわらじはとても柔らかく、
天然のクッションに足が守られているような心地よさは、
どこまでも走っていけそうで
意気揚々と飛び出していったものだ。
今、私は娘とラフィアを編みながら
そんな幼少期の記憶が走馬灯のように蘇ってきた。
私が藁にも似たこの天然の素材の感触と
編む音が好きなのも
そんな幼少期のお祭りの活気と安心感が原体験としてあるからなのかもしれない。
あの日、
目を釣り上げて神輿を担ぎ、
路上で酒を飲み交わし、
警察官の前で堂々と喧嘩をしていた
あの血気盛んな父親達は、
今では、目尻を下げて、体にきたがたの数を自慢し合って笑っている。
その仲間達も、一人また一人と減っていく中、
お祭りは、もう2年行われていない。
ラフィアを編む自分の指先と、
わらじを編む父の指先とが重なるように見えた時
当時の父親達の姿と町の活気が鮮明に蘇ってきた。
温かい気持ちで、またラフィアを編む。
あの日の父のような静かな喜びが、
私から滲み出ているかは分からないけれど、
この心地よさ、
丁寧に編まれた物の柔らかさ、
「大事にされている」という感覚が、
娘達にも伝わることを願いながら。










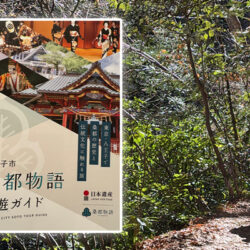










コメント