昨年の夏、私は大豆栽培に失敗した。
枝豆で食べるつもりが、収穫適期を過ぎて茶色くなってしまい、
大豆にして収穫するつもりが、豆は弱々しく、どうにも採る気が起こらないまま、畑に植えていた。
そして秋も終わる頃、大豆は枯れてしまった。
土と同化するように倒れた大豆を1本抜いてみると
根は末広がりに伸び、ひげ根や根粒をつけていた。
抜き終えた後の土は、足が沈むほどふかふかだったのが、印象的だった。
私は、この年の大豆栽培を「失敗」と捉えていた。
収穫できなかったのだから。
人の口に入らないままでその命を終わらせた大豆は、
なんのために植えたのかさえ、説明がつかない。
農や家庭菜園という枠で考えれば、失敗と考えるのが当然だ。
少し悲しい気持ちの残る大豆栽培だった。
年が明けた今春、前年の冬に植えた、ニンニク、玉ねぎ、長ネギが生育を加速させている。
その中で、一つの畝だけ、野菜の生育がすこぶるいい。
他の畝との条件の違いは、前年に植えた野菜の違いだけである。
そして、野菜の生育が活発なその畝が、正にあの「大豆栽培に失敗した畝」だったのだ。
調べてみると、
大豆などのマメ科の根に共生する根粒菌は、大気中の窒素を、土の中の養分としての窒素に固定する働きがある。
つまり、大豆には、土の養分を蓄える働きがあり、土を良くするために自然栽培の初期にも植えられる野菜であるという。
あの食べられなかった大豆は、土を肥やし、その命はこうして翌年の野菜に引き継がれていたのだ。
昨年の大豆栽培を「失敗」だなんて烙印を押したことを、申し訳なく思うとともに、大豆に感謝の気持ちが湧いていた。
無駄な命なんてない。
意味のない命なんてないんだ。
土に引き継がれた大豆の営みを慈しむように、私は土を撫でた。
そして7年前、小松菜の栽培に失敗した時の光景を思い出していた。
あの時も、同じように収穫適期を過ぎ、小松菜は黄色い花を咲かせて風に揺れていた。
こうなってはもう食べられない。
栽培に「失敗した」と思ったけれど、目の前の光景は「失敗」と呼ぶにはあまりにも美しかった。
小松菜の黄色い花に、可憐なミツバチが数匹訪れて、花の蜜を吸っていた。
花と戯れるその姿はとても可愛らしく、まるで春を喜んでいるようだった。
花が咲いたら「失敗」
人が美味しく食べられたら「成功」だなんて、
自然に対して、なんて小さい視点で見ているんだろうと気付かされる体験が時々起こる。
生きていく、食べていくための栽培なのだから仕方のないことだけれど、
自然はもっとずっと大きな摂理の中で動いていることに気づかせてくれる。
私は、人の小ささを思い知る度に、自然の大きさを感じて嬉しくなる。
その存在が大きければ大きいほど、安心する。
親の愛を求める子どものように、
自然の営みに触れると、
大きな懐に抱かれているような安心感を覚えるのだ。
なんて居心地がいい世界なんだろう。
畑という小さな世界でも、その存在に抱かれることができる。
だからここは、私にとっての安全地帯であり、
大人になった今でも安心して子どもに返れる、私の大切な居場所。
それが私だけではなく、他の植物や生き物にとっても安全地帯となるような、
そんな畑を作れたらいいなと思う。










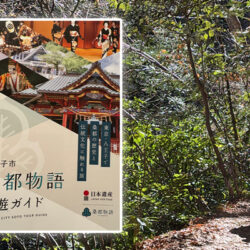









コメント